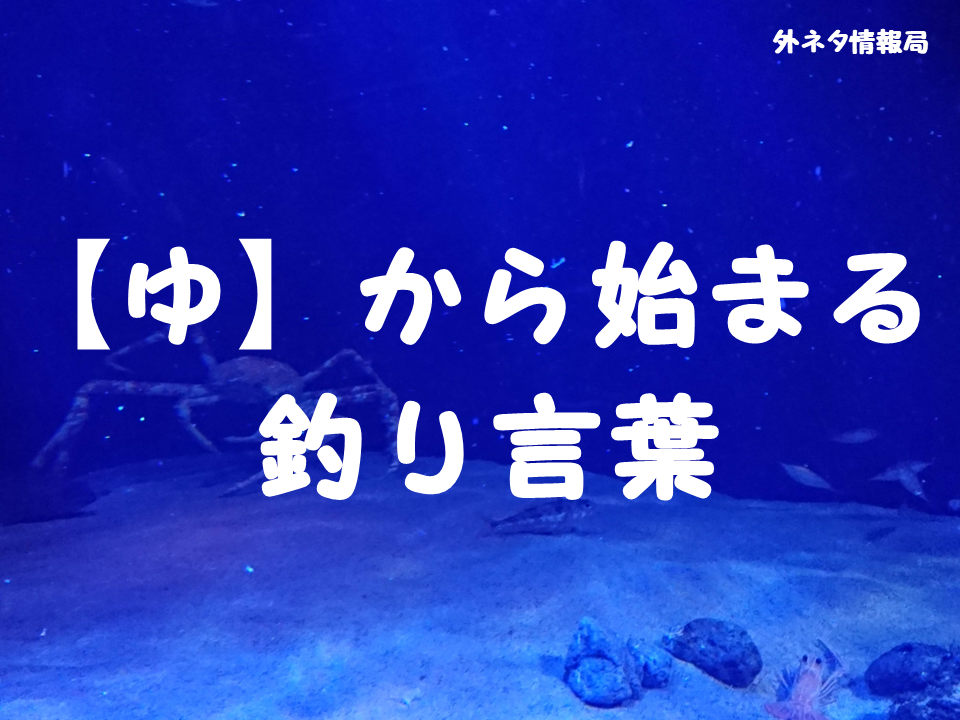「ゆ」の釣り言葉・釣り用語(収録数:10単語)
・弓角(ゆみづの)
魚の骨やプラスチックなどで作られた、弓なりに反った形の疑似餌(ルアー)の一種。主にサーフ(砂浜)や堤防から、ジェット天秤などと組み合わせて遠投し、青物を狙う際に使われます。
・夕マズメ(ゆうまずめ)
日の入り前後の薄暗い時間帯のこと。魚の警戒心が薄れ、捕食活動が活発になるため、釣りの絶好のチャンス(プライムタイム)とされています。「朝マズメ」の対義語です。
・遊漁船(ゆうぎょせん)
料金を支払い、釣り客を乗せて沖の釣り場まで案内してくれる船のこと。船長が釣れるポイントへ連れて行ってくれるため、陸からは狙えない魚種や大物を狙うことができます。
・遊漁券(ゆうぎょけん)
河川や管理釣り場などで釣りをする際に必要な入漁券・釣り券のこと。日釣り券・年券などがあり、漁協等が発行・管理します(地域によって必要・不要があるため確認が必要)。
・誘導式(ゆうどうしき)
ウキやオモリなどを道糸に固定せず、自由に動くようにした仕掛けのこと。「遊動仕掛け(ゆうどうしかけ)」とも言います。魚がエサを咥えたときに違和感を与えにくく、食い込みが良いという利点があります。
・遊動ウキ(ゆうどううき)
ウキを糸や仕掛けに固定せず、水中で流れやアタリに応じて自由に動くようにしたウキ。遊動仕掛けの一部で、魚のアタリがとりやすくなるように使われます。
・ユニノット
釣り糸の結び方(ノット)の一つ。フック(釣り針)やルアー、サルカンなどを結ぶ際に用いられる、非常に信頼性が高くポピュラーな結び方です。
・雪代(ゆきしろ)
春先に山々の雪が解けて、川に流れ込む冷たい水のこと。雪代が入ると川の水温が急激に下がり、魚の活性が低くなることがあるため、特に渓流釣りでは重要な要素となります。
・ユムシ
主に投げ釣りで、マダイやクロダイ(チヌ)などの大物を狙う際に使われるエサ。独特の見た目を持つ環形動物で、非常に匂いが強く、集魚効果が高いことで知られています。
・有効棚(ゆうこうだな)
その日の状況で、最も魚の反応が良い水深(層)のこと。魚は常に同じ水深にいるわけではないため、この有効タナを見つけ出すことが釣果を上げる鍵となります。
・遊泳層(ゆうえいそう)
魚が遊泳して活動している水中の「層」。いわゆる“タナ”のこととほぼ同じ意味で使われることがあります。魚種や時間帯により魚がどの層にいるかを意識することが釣りには重要です。
・揺りかご釣り(ゆりかごづり)
特にワカサギ釣りなどで見られる釣法の一つ。仕掛けをゆっくりと上下させ、まるで揺りかごのように動かすことで、魚にエサをアピールし、食いを誘うテクニックです。
・湯引き(ゆびき)
釣った魚の調理法の一つ。皮と身の間にある旨味を残すため、皮付きのままサクにした魚の皮目に熱湯をかけ、すぐに氷水で冷やす手法です。マダイやイサキなど、皮が美味しい魚でよく用いられます。
・U字メソッド(ゆーじめそっど)
主に渓流や本流でのルアーフィッシングで使われるテクニック。川の流れを利用し、ルアーを対岸に投げてから下流に流し、自分の正面あたりでU字を描くようにターンさせることで、魚の捕食スイッチを入れる誘い方です。
・ユーティリティロッド
汎用性の高いロッド(釣り竿)を指す呼び名。ライトゲームや複数の釣りをカバーする“何でもこなせる”ロッドとしてメーカーやメディアで紹介されています。
.png)